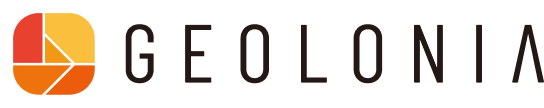FIWAREって何?スマートシティの「リアルタイムデータ」活用の鍵
「スマートシティ」や「DX」といった言葉とともに、「FIWARE(ファイウェア)」というキーワードを耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか? 特にデジタル関連部署に配属されたばかりの方にとっては、「聞いたことはあるけど、具体的に何なのかよくわからない…」と感じているかもしれません。
今回のブログでは、そんな「FIWARE」について、できるだけ専門用語を使わずに、分かりやすく解説していきます。FIWAREがどんなもので、スマートシティでどんな役割を果たすのか、そして私たちGeoloniaが提供する「地理空間データ連携基盤」とどう連携できるのかについてお伝えします。
FIWAREって、そもそも何?
FIWAREとは、スマートシティなどで使われる「リアルタイムデータ」を扱うのが得意な、オープンソースのプラットフォームです。
オープンソースとは、ソフトウェアの設計図(ソースコード)が公開されていて、誰でも自由に利用、改変、再配布できるソフトウェアのことです。特定の企業に縛られず、柔軟にシステムを構築できるメリットがあります。
FIWAREが得意とする「リアルタイムデータ」とは、例えば以下のような、常に変化する動的な情報を指します。
- 駐車場の満空情報
- 街なかのセンサーが計測した温度や湿度
- 避難所の開設状況や混雑度
- 河川の水位
これらの「今、どうなっているか」という情報を、効率的に収集・管理・提供するための共通のルール(データモデルやAPI)を提供してくれるのがFIWAREです。
スマートシティにおけるFIWAREの役割
スマートシティの実現には、街の様々なデータを連携させ、新しいサービスを生み出すことが不可欠です。FIWAREは、特にセンサーなどから得られるリアルタイムデータを扱う共通基盤として、ヨーロッパを中心に多くの都市で導入されています。
これにより、例えば以下のようなサービスの実現が期待されています。
- リアルタイムの交通情報に基づいた最適な経路案内
- センサーデータと連携した効率的なエネルギー管理
- 災害発生時のリアルタイムな避難誘導
FIWARE を導入した自治体の「よくある悩み」
FIWAREはリアルタイムデータを扱う上で非常に強力なツールですが、導入した自治体から、しばしばこんな声が聞かれます。
- 「プラットフォーム(箱)は導入したけれど、肝心のデータ活用が進まない…」
- 「リアルタイムデータ向けのはずなのに、更新頻度の低い地図データや統計データまでFIWAREに入れようとして、管理が大変だしコストもかかる…」
- 「新しいデータを追加したり、運用したりするのに専門知識が必要で、思ったより費用がかさむ…」
これは、FIWAREが本来得意ではない静的な地理空間情報(地図データなど)まで扱おうとしたり、ユースケースを考えながら投入するデータを決めるような企画のプロセスが欠如していたり、データを使うアプリケーションの開発が思うように進まなかったりすることが原因の場合が多いようです。結果として、FIWAREとデータのやりとりをする必要のないサービスから出てくる利用実績などのデータを入れていたり、既存の静的なデータを職員さんたちが自分の手で入力するような苦労も見受けられます。
解決策は「得意」を組み合わせること:FIWARE + 地理空間データ連携基盤
ここで、私たちGeoloniaが提唱する「地理空間データ連携基盤」が登場します。
「地理空間データ連携基盤」は、地図データ(地理空間情報)を効率的に管理し、様々なアプリケーションで「共通の地図」として簡単に利用できるようにすることに特化した基盤です。これは、国のスマートシティリファレンスアーキテクチャ(SCRA)でも、都市OSの中核機能の一つとして位置づけられています。
FIWAREと地理空間データ連携基盤は、お互いの「得意」を活かして補完しあう関係にあります。
- FIWARE: センサーデータなどの「リアルタイムデータ」の収集・管理・提供が得意
- 地理空間データ連携基盤 (Geolonia): 地図データや施設情報などの「静的・準静的な地理空間データ」の統合・管理・配信が得意。また、APIとSDKを使うとアプリケーションの開発工数やコストが大きく下がる点でサービスの開発が得意
この二つを組み合わせることで、それぞれのプラットフォームが得意な仕事に集中でき、スマートシティ全体のデータ活用がより効率的かつ低コストになります。

FIWAREと地理空間データ連携基盤の連携イメージ
具体的に、どのように連携できるのでしょうか? 主な連携方法は2つあります。
- 地図アプリの高度化: 地理空間データ連携基盤で作られた地図アプリ(例えば、観光案内マップやハザードマップ)があります。このアプリが、FIWAREが管理しているリアルタイムデータ(駐車場の満空情報、避難所の開設状況、ライブカメラ映像など)を取得し、地図上に重ねて表示します。これにより、ユーザーは地図を見ながら「今」の状況を把握でき、より便利で高度なサービスが実現します。水位が上がっていたらアイコンを赤くしたり注意のメッセージを表示したり、駐車場の空き状況を見ながら駐車場料金の調整や道案内ルートを変更したりするなど、FIWAREの情報を使って街の効率的な運用に使うこともできます。
- 空間IDによるデータ連携: FIWAREが管理するセンサーなどの設置場所や観測範囲を「空間ID」(特定の場所や範囲を示す3次元空間での共通の住所のようなもの)で管理します。アプリケーションは、この空間IDをキーにして、FIWAREからはリアルタイムデータを、地理空間データ連携基盤からはその場所の地図情報や関連情報を取得し、簡単に紐づけて利用できます。「この建物の今の温度は?」「この交差点の現在の交通量は?」といった要求に、スムーズに応えられるようになります。
空間IDについては、今後もスマートシティブログのなかで発信していきますので、詳しい仕組みについてはもう少しお待ち下さい。
自治体にとってのメリット
FIWAREと地理空間データ連携基盤を連携させることで、自治体には以下のようなメリットが生まれます。
- FIWAREへの投資効果向上: 導入済みのFIWAREをより有効に活用できます。
- 迅速・低コストなアプリ開発: 地図関連のデータ準備や連携の手間が大幅に削減され、住民向け・職員向けサービスを素早く開発できます。
- 効率的なデータ管理: 地図データは地理空間データ連携基盤、リアルタイムデータはFIWARE、と適切な役割分担で管理コストを最適化できます。(Geoloniaの基盤では、地理空間データの追加・更新は原則無料です)
- 国の推奨アーキテクチャへの準拠: スマートシティリファレンスアーキテクチャ(SCRA)が示す、データ連携の考え方に沿ったシステム構築が可能です。
まとめ:スマートシティの実現に向けて
FIWAREは、スマートシティにおけるリアルタイムデータ活用のための重要なプラットフォームです。しかし、それだけで全てのデータ課題が解決するわけではありません。
特に、あらゆるサービスの基盤となる「地図データ」については、専門の「地理空間データ連携基盤」と組み合わせることで、FIWAREの価値を最大限に引き出し、より効率的で効果的なスマートシティサービスを実現できます。
Geoloniaは、この「地理空間データ連携基盤」の提供を通じて、FIWAREを導入済み、あるいはこれから導入を検討している自治体の皆様が、データ活用をスムーズに進められるよう支援します。
「FIWAREと地図データの連携について、もっと詳しく知りたい」「うちの自治体の場合、どう活用できるか相談したい」など、ご興味を持たれましたら、ぜひお気軽にGeoloniaまでお問い合わせください。